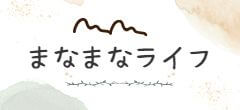梅雨明けとともにやってくる夏休み。
1学期の終わりに手渡された夏休みの宿題のせいで、「やったぁ!」と喜んでばかりはいられないお子さんも多いのではないでしょうか。
今回は小学生のお子さんをお持ちの保護者の方々を対象に、夏休みの宿題の攻略法を紹介します。
ちなみに、私が以前勤務していた米軍基地内の学校も含め、アメリカの学校には夏休みの宿題というものがありません。おかげで2か月半もある夏休みは、子どもたちにとって「待ちに待った楽しみ」以外の何物でもありません。
夏休みの宿題の取り組み方

地域によって、あるいは学年によって、夏休みの宿題は少しずつ違いますが、
- 教科学習のドリル(プリント)
- 絵日記
- 工作または自由研究
- 読書感想文
あたりが一般的なところではないでしょうか。
教科学習のドリル(プリント)
教科学習のドリル(プリント)は、夏休みの宿題の中でもはっきりと「量」が見えるタイプの宿題です。
終わった量とまだの量が一目瞭然ですし、全部終わらせるのにどれくらいの時間・日数が必要かわかるので、計画的にこなしていけば、確実に終わらせることができるはずです。
けれどこのタイプの宿題は一番おもしろくない宿題でもあります。
1学期の復習問題を機械的に解いていくのは、勉強というより単純作業の繰り返しでしかありませんし、大人でも同じだと思いますが、今ひとつやる気が起きないうえに、やり始めてもすぐに飽きてしまう子も多いと思います。
なので、よく言われる「子どものペースに合わせて、毎日1時間ずつ」のような取り組み方ではうまくいきません。
お勧めは、夏休みの初めにとにかく全部のドリル(プリント)を終わらせてしまうことです。
「つまらなくてもやるしかないなら、まとめて一気に片付けよう」と、開き直ったほうが効率も上がります。
目に見えるタイプの宿題は、身体がまだ学校生活のリズムで動いている間に、「このつまらない宿題が終わったときこそ、本当の夏休みの始まりだ!」とばかりに、夏休みの初日から開き直って一気に終わらせよう!
絵日記
絵日記もあらかじめやらなければいけない量(ページ数)が決まっていて、やったかやらないかがひと目でわかるタイプの宿題です。
けれど教科学習のドリル(プリント)と違って、一気にまとめて終わらせるやり方向きではありません。
このタイプの宿題は、あらかじめやる(日記を書く)日を決めておきます。
なお、日記を書く日ですが、必要なページ数分だけ適当に日にちを選ぶのではなく、普段とは違う活動やイベントが実行可能な日を選びます。というより、夏休みの予定に日記に必要なページ数だけ、活動やイベントを組み込みます。
もちろん全部の活動に親が一緒に参加する必要はありませんし、金額の張る大イベントである必要もありません。例えば、一緒にスーパーに買い物に行くのも、友だちとゲームをするのも、非日常という意味においては立派なイベントです。
さらに、その活動やイベントの様子をできれば写真に撮っておきましょう。絵を描く時の参考にもなりますし、親子の楽しい会話の機会も生まれますので。
夏休みの予定に、絵日記に必要なページ数分の活動やイベントを組み込み、その日を「絵日記を書く日」と決めておこう。活動中の写真を撮っておくと、あとが楽だよ。
工作または自由研究
夏休み明けのコンクール入賞を目指しているのでない限り、工作や自由研究は1‐2日で終わるもの、実験などはたとえ日数がかかってもほとんど手をかけなくていいもの、自分が楽しめること・興味を持っているものを選びます。
取り掛かるのは教科学習のドリル(プリント)を終わらせた後のいつでも構いませんが、こちらも「いつか」ではなく、やる日を決めておくようにします。
絵日記を書く予定の日に工作を入れておけば、2つの宿題が1度に片付いて一石二鳥です。
自由研究に何かの観察日記をつけるのであれば、絵日記の取り組み方が参考になります。
なお、お勧めの工作や自由研究については、後述の「工作・自由研究のアイデア」の項をご覧ください。
工作または自由研究は、教科学習のドリル(プリント)を終わらせた後ならいつでもいいので、あらかじめやる日を決めておきましょう。
読書感想文
読書感想文は、まず本を読まないことには書けません。(まぁ、書評や抜粋を参考に書こうと思えば書けますが、小学生のころからそんなずるをさせたい親はいないと思いたいです。)
つまり、この宿題を終わらせるには、「本を読む」と「感想文を書く」の2種類の作業と時間が必要です。
そこでお勧めなのが、夏休みの早い段階から、①毎日寝る前の15-30分を読書の時間に充てる、②次の日の朝、前日の夜に読んだ個所のまとめや感想を家族に伝える、③読み終わった次の日に感想文を仕上げるという3ステップ方式です。
特に②は最終的な感想文を書く際の下準備になるので、文章を書くのが苦手な子どもでも長文が書きやすくなるという利点があります。
読書感想文は、夏休みの早いうちから、毎日就寝前の短時間に少しずつ本を読み、読んだところのまとめや感想を次の日の朝に家族に話し、全部読み終わった次の日に感想を仕上げる3ステップ方式でやっつけよう。
*毎年の課題図書はこちらで確認できます。また、本屋に行かなくても、以下のお店で注文が可能です。
夏休み中に宿題を終わらせる秘訣

取り組み方の異なる数種類の宿題を夏休みの最終日までに終わらせる秘策は、
- 宿題の「見える化」
- やる気
の2つです。
宿題の「見える化」
前述のとおり、目に見えない宿題も、必要な日数を計算してあらかじめやる日を決めることで「見える化」できます。
まずは見逃しようのないサイズの計画表(カレンダー)を作り、嫌でも目につくところに貼ります。
そして計画表(カレンダー)ですが、何をいつやるかがわかるだけでなく、進捗状況(終わったか終わっていないかも含む)もわかるようにします。
実際のところ、この計画表(カレンダー)は、夏休みの宿題を期間中に終わらせられるかどうかを左右するくらい重要です。
「教科学習のドリル(プリント)」は夏休みの初日から始める」ように勧めましたが、計画表作りはそれよりも前にやっておきましょう。
やる気
たとえ計画が完璧でも、実行する人間にやる気がなければ、何事も計画倒れで終わってしまいます。
夏休みの宿題を計画に沿ってこなしていくには、本人のやる気が必須です。
ではどうすれば、遊びたい盛りの子どもから宿題をやる気を引き出せるでしょうか。
お勧めは宿題をゲーム化することです。
例えば、学習ドリルは「レベル1」、読書感想文は「レベル2」のように名前を変え、やった量やページ数に合わせて、「経験値が3Upした」、各宿題が完了したあかつきには、「レベル1クリア」と言って、メダルやバッジを与えます。低学年の子どもには折り紙や厚紙を使って手作りしたもの、高学年の子どもにはデジタルバッジが好まれます。
「もう○○(の宿題)終わったの?」より「レベル3、クリアした?」、「今日は何ページ終わったの?」より「今日は経験値が何Up?」のほうが、言うほうも言われるほうも楽しい気分になりますよ。
*デジタルバッジのサンプルが欲しい方はこちら↓(Word等に表を作って貼り付けたり、PCやタブレットなどのデスクトップにそのまま貼り付けられます。)



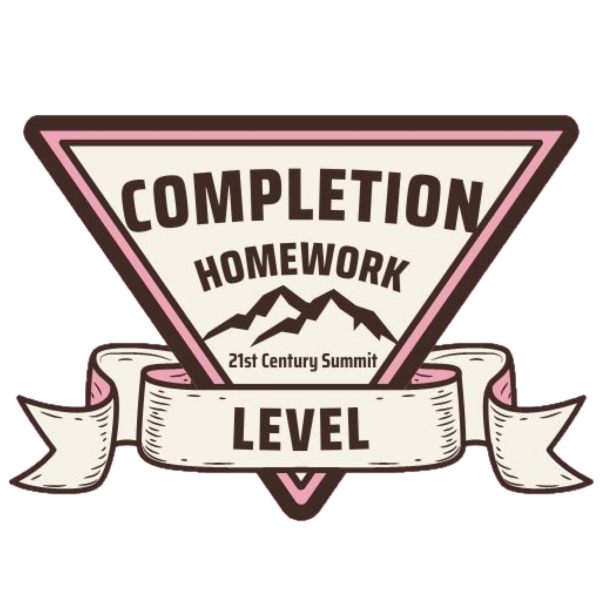


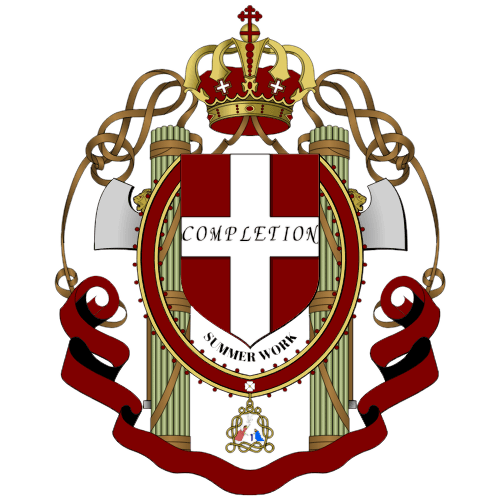

サンプルをもっと見たいという方は「登録不要・無料ダウンロードのイラスト素材(アイテム・ツール・アイコン編)」をチェック!
*上のサンプルは「Canva(無料プラン)」+「ペイント3D」で作りました。
Canvaの「デザイン作成」で「ロゴ」を選択→素材(グラフィック)の中から好みのバッジデザインを選んで編集→「JPG」でダウンロードし、PC内に保存→「ペイント3D」で背景を透過。


工作・自由研究のアイデア

始めに断っておくと、私がお勧めする工作・自由研究ではたぶんコンクール入賞は狙えません。けれど悩みの種の宿題を楽しめると思います。
オンラインゲーム制作
ゲーム好きな子にうってつけなのが、授業で習ったScratchを使ったオンラインゲーム制作です。
ただ、「いくら子どもが自主的にやってくれそうな工作(?)でも、プログラミングのことなんて全くわからないから、親としてサポートのしようがない」と二の足を踏む保護者の方もいらっしゃると思います。
そんな場合には、オンラインのプログラミング教室を試してみるのも1つの手です。夏休みが終わっても、そこで得る知識やスキルは学校の授業で役立ちますし、何よりもゲームにはまっているお子さんを「する」ほうから「作る」(学習)に誘導できます。
因みに「ScratchでGo」なら、「やる気」の項で紹介した「経験値」を追加したり、レベルアップが可能なゲームも作れるそうです。
*この宿題の提出は、作ったゲームのリンクを送る(渡す)だけです。
高齢者観察日記(自由研究)
もしお盆あたりに実家に帰省する計画があるなら、高齢者観察日記をお勧めします。
タイトルは日記ですが、中身は、
- 対象者(おじいさん・おばあさん)に関する基本情報(インタビュー)
- 平均的な1日のスケジュール(観察)
- 考察(気づき)
- 今後の課題
の4項目からなる自由研究です。
高齢化社会の問題に目を向けさせるだけでなく、おじいちゃん・おばあちゃんと有意義な時間を過ごせるのが最大のポイントです。
野菜・フルーツ栽培
普段何気なく捨てている野菜やフルーツの種を育ててみましょう。
ピーマン、トマト、アボカド、スイカ、カボチャ、桃など、どんな種でも、1種類でも、何種類でもOK。たとえ芽が出なくても、最終的に実にならなくてもOK。
「理科の実験」と聞くと、スタートからゴール(この場合、植え付けから発芽、または実になる)までを網羅していないといけないと思いがちですが、①仮説を立て、②リサーチで情報を集め、③途中までの記録をまとめ、④記録を分析・考察し、⑤今後の課題や推察を述べれば、それで立派な研究になります。
おそらく一番時間がかかるのは、植え方についてのリサーチで、あとはほったらかしでいいので、動画大好きっ子の面倒くさがり向きの自由研究です。
飾りもの工作
きれいやかわいい系が好きな子には飾りもの作りがお勧めです。
- 押し花を貼り付けた和紙ライト
- 材料:和紙(障子紙や半紙でもOK)、木工用ボンド、押し花、100均のLEDライト
- ストーンアート
- 材料:海岸などで拾った丸っこい石、アクリルペイント
- 苔テラリウム
- 材料:苔、ジャムなどの空き瓶、土(砂利)、小石や枝
- 木の実のリース
- 材料:土台(段ボール・わらなどなんでも)、拾ってきた木の実、グルーガン+グルー(ボンドよりもちゃんと接着します)
どの工作も自然散策で手に入れたものをベースにしています。お金も時間もさほど使わないのに、プロ顔負けのものができちゃいます。
親子で一緒に作るのも楽しいと思います。
その他のおすすめ
- 家系図作り:自分はいったいどこから来たのか、たどれるところまでたどっていきます。仏教徒なら、おじいちゃん・おばあちゃんのおうちの「過去帳」が役に立ちます。
- 「あったらいいな」製品の設計図作り:子どもはしょっちゅうアッと驚くような発想をする発明家の卵です。実際に思いつた物を作るのは、親の協力があっても難しいかもしれませんが、詳しい説明付きの設計図なら簡単に書けます。もしかすると大ヒット商品が生まれるかも。
- だれでもユーチューバー:オリジナルのダンス・歌・漫才などのパフォーマンス、現場リポートやクッキングの様子などを録画(録音)します。友だちとの共同制作も可能。こちらも提出はリンクのみ。
最後に

ところで、夏休みの宿題が終わらなかったからといって、何も人生が終わるというわけではありません。
実際、学習指導要領には宿題に関する記述がないので、宿題をしなかったせいで成績が下がることはないはずです。
訂正:
文科省は学習状況の判断評価を
- 「知識・技能」
- 「思考・判断・表現」
- 「主体的に学習に取り組む態度」
の3つの観点から行うよう指導しています。
つまり、「宿題をやらない・期日までに終わらせない=主体的に学習に取り組む態度に問題あり」ということで、成績にいくらか影響が出ることは確実です。
小学生ではありませんが、私の中1の甥っ子は夏休みの友を10月1日に提出した強者です。
他にもしょっちゅう提出物を遅れて出すか、出さずじまいに終わっているようで、それが原因で「どれだけテストでいい点を取っても、通知表では最高の評価は付かない」と担任に言われたそうです。
もう1つ、2学期が始まった時点で宿題が全部終わっていなければ、お子さんはまず間違いなく、学校で恥かしい思いやみじめな思いをするでしょう。
「それじゃあ、子どもがかわいそうだから」と、近年、代わりに宿題を終わらせる親が増えてきているようですが、それで子どもが学ぶのは「ズルをしても、うまくごまかせればいい」「困ったら親が何とかしてくれる」ということだけで、教育的には問題が大ありです。
本当に子どものためを思うなら、自分の行動の責任は自分で取らせるべきです。すべきこと(と思われていること)をしないと、どんな結果が待ち受けているのか身をもって学ぶほうが、子どもにとってはずっといい人生勉強になります。
夏休みには夏休みにしかできないことがたくさんあります。学校の宿題を終わらせることも大事ですが、同時にせめて夏休みの間くらい親子一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
\このブログがお役に立ったなら/

年齢も性別も国籍も種族(?)も超えた人たちが集まって、互いに学びあい、喜びや楽しみを分かち合えるコミュニティサロンの設立・運営にご協力をお願いします。