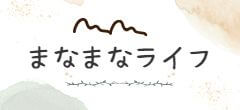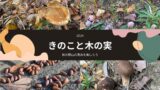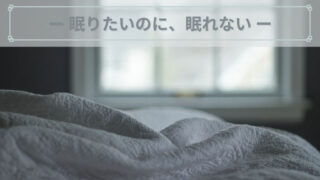毎年春になると、裏山にわらびやぜんまい、タラの芽やコシアブラを採りに入るのが恒例でしたが、今年は寒波がぶり返したりして、なかなかいいタイミングで出かけられません。
そこで目についたのが家の周りに大量に咲いているヤブツバキ。
子どもの頃を思い出して、花をむしっては半分に割って中の蜜をなめてみましたが、いま一つ満足感が得られません。
山になった花の残骸を見て、もっと何か生産的なことができないかと思い調べたところ、花からも葉っぱからもお茶が作れると分かりました。
もしやと思い、同じように蜜を吸っていたシロツメクサについても調べると、こちらもお茶にできるとあります。
結局、これまで厄介者だと思っていたたくさんの山野草(自生している草木)から、同じくお茶が作れることが判明しました。しかもそのお茶には、
- 材料集め(樹木の整備や草取り)が、①生物の多様性や生態系の保全、②環境負荷の軽減、③美しい景観の維持につながるため、SDGsの目標15「陸の豊かさも守ろう」につながる
- 大切に育てている野菜以上の健康効果が期待できる
というおいしいおまけまでついています。

そこら中、お宝だらけじゃない!
ということで、今回は出雲に限らず、国内の割とどこででも見つけられる18種類の山野草を使った和製ハーブティーともいえるお茶の作り方と、それぞれの山野草の成分、期待できる健康効果について紹介します。
野草茶
野草茶とは、自生している草木の根・茎・葉・花等を採取し、洗ったあと、①乾燥、②乾燥⇒焙煎、③乾燥⇒蒸す⇒焙煎、または④生をそのまま煮出して淹れたお茶のことです。
*新芽や開花の季節など、採取に最適な時期はありますが、基本的にはいつ採取してもOKです。
*乾燥は、物干し網に入れる、吊るす、食品乾燥機を使うなど、何でもOKです。(私はざるで水気を切った後、新聞紙の上に広げて乾かしています。)
乾燥した茶葉を粉状に粉砕させれば、栄養分を丸ごと体に取り込めます。
使う植物によって独特の風味が楽しめるだけでなく、多くは漢方薬の原料になるくらい身体にいい成分を含有しています。
採取の際の注意点
森林法
野草茶の材料のほとんどは、いわゆる雑草です。
例えば、道路わきに大量にはびこる雑草を採ったからといって、問題になることはほぼほぼないでしょう。
けれど、どこかの庭先や畑の脇、公園や山中に生えているものとなると、「森林法」が声高に主張してきます。
土地には必ず所有者がいます。それが国であれ、地方公共団体であれ、個人であれ、そこに生えているものを所有者の許可なく採るのは違法です。
毒性
お茶にできる雑草の中には、よく似た見た目の植物がいくつもあって見極めが難しいものがあります。ほとんどは無害ですが、毒草も無きにしも非ずなので、確信が持てないときは採らないのがいちばんです。
汚染
交通量の多い道路沿いや駐車場脇に生えている植物は、排気ガスに汚染されている可能性が高いので、飲用には不向きです。
現在進行形で活用されている畑や田んぼの脇も、農薬に汚染されている可能性があります。
ペットの散歩コース付近も、糞尿がかかっている危険性から、避けるのが無難でしょう。
服装
山野草を採りに行くときは、服装に注意しましょう。
草むらや藪の中には、毒のある蛇やハチ、毛虫などのほか、マダニのように目に見えない脅威も潜んでいます。
飲用の際の注意点
いくら健康効果が期待できるからといって、短期間に大量のお茶を飲むのはよくありません。野草茶は効果が出るまでに時間がかかります。
少量ずつ継続的に飲んだにもかかわらず、体調不良になった場合も、飲用を中止すべきです。残念ながら、人によって合う合わないがあるからです。
また、妊婦さん、授乳中、乳幼児、アレルギー体質、薬を服用中の人などは、飲んでも問題ないかお医者さんに相談したほうが安心でしょう。
保存の際の注意点
日陰干しで乾燥させただけの野草茶は、乾燥剤と一緒に密閉できる容器(ガラス瓶やジップロックバッグなど)に入れて、湿気の少ない冷暗所で保管します。
地域にもよると思いますが、日陰干しのまま放置しておくと、梅雨の時期に水分を含んでカビが生えたり虫が湧くことがあるのでお勧めしません。
ツバキ(ヤブツバキ)

基本情報
ツバキはお茶の原種です。
自生しているものに限らず、園芸種のツバキも秋に花をつける山茶花も同種です。
| 採集時期 | 2~4月 |
| お茶に使う部位 | 花・蕾・葉 |
| 主な成分 | オレイン酸、リノレン酸、没食子酸、ケルセチン、アントシアニン、ユゲノール、 タンニン、クロロフィル、ツバキサポニン、テアフラビン |
| 期待できる健康効果 | 花:滋養強壮、健胃、整腸、抗酸化作用・抗炎症作用、美白効果、 アンチエイジング効果 葉:関節痛の緩和、血糖値の上昇抑制、血圧抑制、体脂肪・中性脂肪濃度の減少、 殺菌効果、リラックス効果 |
| お茶以外の利用法 | 生の葉の汁:切り傷・擦り傷・皮膚の炎症 花・つぼみ:シロップ・酢の物・天ぷら |
ツバキ茶の作り方
花茶
- 花びらを水洗いする
- 水気を取り、陰干しで1週間くらい乾燥させる(花びらの色は紫っぽくなる)
乾燥した花びらに熱湯を注げば、ツバキの花茶の出来上がり。
*花びらだけでなく、花一輪や蕾をまるごと乾燥させてお茶にすることも可能です。その場合、花粉も入っているため、花粉症の人には向かないと思います。
花茶(まなまなバージョン)

- 花をガクから外す
- 下のほうを絞って蜜を出す
- 花びらをむしり、水洗いする
- 水気を採り、陰干しで乾燥させる
蜜の甘さを花茶に活かしたかったので、洗う前に絞り出してみました。
そのままにしておくと発酵してしまうので、私は一応レンチンして火を通し、花びらが乾燥するまで密封した容器に入れて冷蔵庫で保管します。(量が少ないと乾いてなくなってしまいます。)
だいたい10個の花から小さじ4分の1くらいしか蜜が採れないので、保存せず、その日のうちに紅茶やハーブティーに入れて飲んだほうがいいかもしれません。
葉のお茶
紅茶系
- 若くてやわらかめの葉をきれいに洗い、できれば蝋質を取りのぞく
- 陰干しでしおれさせる
- 押しつぶすというより転がすようにして手でもむ
- 高めの湿度のところにおいて、さらにしおれさせる
- フライパンで乾煎りして、完全に乾燥させる
緑茶系
- 若くてやわらかめの葉をきれいに洗い、できれば蝋質を取りのぞく
- 蒸す
- 押しつぶすというより転がすようにして手でもむ
- フライパンで乾煎りして、完全に乾燥させる
ウーロン茶系
- 若くてやわらかめの葉をきれいに洗い、できれば蝋質を取りのぞく
- 日陰干しでしおれさせる
- フライパンで乾煎りする
- 押しつぶすというより転がすようにして手でもむ
- フライパンで乾煎りして、完全に乾燥させる
胃腸の働きを改善したり、リラックス効果が期待できるので、寝起きに飲むのがおすすめ。
アカマツ

基本情報
松葉茶に使われるアカマツは、針のような葉の先端を触っても痛くありません。
幹の色や冬芽の色が赤茶なので、クロマツと見分けるのは比較的簡単です。
| 採集時期 | 5~7月 |
| お茶に使う部位 | 葉 |
| 主な成分 | ケルセチン、スラミン、テルペン精油(α-ピネン)、ビタミンA・C・K、 鉄分、カルシウム、カリウム、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、バリン、ヒスチジン、クロロフィル、フラボノイド |
| 期待できる健康効果 | 動脈硬化予防、高血圧症予防、認知症予防、利尿作用(デトックス)、滋養強壮、 貧血の改善、呼吸器症状の緩和、疲労回復、ストレス緩和、抗炎症・抗ウイルス作用 |
| お茶以外の利用法 | 入浴剤・精油 |
松葉茶の作り方
- 若くてやわらかい葉から付け根の茶色い軸の部分を取り除く
- 水洗いしたのち、陰干しで乾燥させる
- 短く切るか、ミルサーなどで粉々にする
切ったものは沸騰させた湯に入れたのち、弱火で5分ほど煎じて飲むのがおすすめです。
*生の松葉を乾燥させずにそのまま煎じて飲むこともできます。北米ではオフグリッド(僻地)でブッシュクラフト生活をしている人たちが、よく生葉をお茶にして飲んでいます。
粉末のほうは急須にお湯を注ぎ、しばらく蒸らした後に飲みます。
脂溶性ビタミンがたくさん含まれているので、脂っこい食事の後に飲むのがおすすめ。
スギ・ヒノキ

基本情報
花粉症の人には天敵の二大針葉樹ですが、葉っぱを使ったお茶にはその花粉症症状を軽減する働きがあると言われています。
| 採集時期 | 4~5月 |
| お茶に使う部位 | 葉 |
| 主な成分 | スギ:フィトンチッド、セドロール、セスキテルペン、スギフェノール、テルペン、 テルピネン-4-オール、タンニン、テレピン油、 ヒノキ:フィトンチッド、ヒノキチオール、カジネン、カジノール、モノテルペン、 αピネン、 セドロール、βカロテン、タンニン |
| 期待できる健康効果 | スギ:アトピー性皮膚炎・スギ花粉症の軽減、殺菌作用、抗酸化作用、 鎮静・鎮咳効果、リラックス効果、抑うつ状態の改善、熟睡効果、 ヒノキ:肌の改善、アレルギー症状・ヒノキ花粉症の軽減、抗菌・殺菌作用、 リラックス効果、ストレス解消効果、不眠症の軽減、 |
| お茶以外の利用法 | エッセンシャルオイル、除菌スプレー、防虫シート、 |
スギ茶・ヒノキ茶の作り方
- 出来るだけ青々しい先端部分を切り取り、水洗いする
- 1~2日陰干しする
- しおれた葉を細かく刻む
- 鍋に水と刻んだ葉を入れ、とろ火でお湯が半分になるくらいまで煮詰める
ステップ2・3をスキップした作り方もあります。
煮出したエキスが濃すぎて飲みにくいかもしれないので、水やお湯で割って飲むといいでしょう。
なお、新芽(花粉症の時期が終わった後に出てくる)を使う場合、しっかりと乾燥させておけば、翌年の花粉症の時期ぴったりにお茶を飲むことができます。
花粉症対策なら、食事の際、または食後、安眠対策なら、寝る1時間ほど前に飲むのが効果的。
クマザサ

基本情報
| 採集時期 | 5~8月 |
| お茶に使う部位 | 葉 |
| 主な成分 | ビタミン、フラボノイド、リグニン、葉緑素、アミノ酸 |
| 期待できる健康効果 | 殺菌・脱臭作用、糖尿病・高血圧・動脈硬化予防、便秘の改善、貧血予防、 血液サラサラ効果、虚弱体質・アレルギー体質の改善、胃弱・胃もたれの改善、 疲労回復、口臭除去 |
| お茶以外の利用法 | 蒸しだんごや笹寿司の包み |
クマザサ茶の作り方
- できるだけ若く柔らかい新芽を水洗いしたのち、水分をふき取る
- 5cmくらいの長さに切りそろえる
- フライパン(中弱火)で香りが出るくらいまで乾煎りする。 (焦げると苦くなるので注意!)
乾燥したクマザサを5分ほど弱火で煮だせば完成です。
粉末茶
- 洗って水気をふき取った葉っぱを天日干しでカラカラに乾燥させる
- ミルサーなどで粉々に粉砕する
粉末のほうは急須にお湯を注ぎ、しばらく蒸らしてから飲みます。
食前、食間、食後、いつでもOK。
淡竹

基本情報
淡竹に限らず、どんな種類の竹の葉や笹でもお茶が作れます。
| 採集時期 | 青葉の時期 |
| お茶に使う部位 | 葉 |
| 主な成分 | 鉄クロロフィリン、安息香酸、ビタミンB・C、食物繊維、葉緑素、カリウム、 カルシウム |
| 期待できる健康効果 | 抗菌・防腐作用、高血圧・貧血予防、細胞の活性化、抗酸化作用、疲労回復、 デトックス効果、熱さまし、血液サラサラ効果 |
| お茶以外の利用法 | 特になし |
竹の葉茶・笹茶の作り方
- 葉っぱを水洗いして汚れ等を取り除いた後、5分ほど蒸す
- ざる等に上げて冷ます
- 汁気が出るまで手でもむ
- フライパンに入れ、香りが出るまで遠火で乾煎りする
急須に熱湯を入れて飲むこともできますが、数分煮出したほうがおいしいです。
クマザサ茶同様、食前、食間、食後、いつでもOK。
サルトリイバラ

基本情報
つる性の植物で、トゲがあります。お茶には使いませんが、赤く熟した実も食用可能です。
| 採集時期 | 4~8月(芽の出始めか、葉が青々としている頃) |
| お茶に使う部位 | 新芽・葉、根 |
| 主な成分 | スミラックスサポニンA・B・C、スミラシン、タンニン |
| 期待できる健康効果 | 排膿解毒作用、消炎作用、利尿効果(むくみの改善)、解熱作用 |
| お茶以外の利用法 | 蒸しだんご等の包み 新芽:天ぷら、あえ物、おひたし、炒め物 |
サルトリイバラ茶の作り方
根のお茶(おできや腫れもの対策)
- 茎やひげ根を取り除き、水洗いする
- 天日干しで乾燥させる
乾燥した根10gほどを400ccくらいの水に入れ、とろ火で水の量が半分になるくらいまで煎じます。(1日分)
食間(空腹時)に、1日分を3回に分けて飲むのがおすすめ。
葉のお茶
- やわらかい葉はそのまま、固い葉は蒸して柔らかくする
- 天日干しかフライパン等で乾煎りして乾燥させる
乾燥した根10gほどを300ccくらいの水に入れ、とろ火で水の量が半分になるくらいまで煎じます。(1日分)
食前か食間(空腹時)に、1日分を3回に分けて飲むのがおすすめ。
スミレ

基本情報
スミレはどの種類でも食用可能です。
| 採集時期 | 3~5月 |
| お茶に使う部位 | 花、葉 |
| 主な成分 | ルチン、ビタミンC、アルカロイド、フラボノイド、サポニン、グリコサイト、 ビオラルチン |
| 期待できる健康効果 | のぼせ解消、抗酸化作用、生活習慣病・糖尿病・出血性疾患・認知症予防、 不眠の改善、リラックス効果、消炎作用、喉の痛みの緩和、去痰作用、 利尿作用 |
| お茶以外の利用法 | サラダ、酢の物、あえ物、砂糖漬け |
スミレ茶の作り方
- 花・葉をやさしく水洗いして、汚れを取る
ティーポットに花・葉を入れて熱湯を注ぎ、好みの色合いになるまで3~5分蒸らしてから飲みます。
いつ飲んでも構わないが、疲れがひどい時や寝る1時間ほど前が効果的。
ドクダミ

基本情報
ドクダミは、ゲンノショウコ、センブリと並ぶ「日本三大薬草」の1つです。
| 採集時期 | 5~6月 |
| お茶に使う部位 | 葉・茎 |
| 主な成分 | カリウム、マグネシウム、鉄分、亜鉛、マンガン、フラボノイド、 ビタミンB群(ビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸)、ビタミンK |
| 期待できる健康効果 | デトックス効果、むくみの改善、動脈硬化・高血圧予防、便秘の改善、血行促進、 抗菌作用、抗ウイルス作用、認知機能改善、肌の老化防止、 |
| お茶以外の利用法 | 葉:天ぷら、あえ物 入浴剤、湿布、チンキ |
ドクダミ茶の作り方
- 茎からまとめて刈り取った葉っぱを流水で洗い、 汚れを落とす
- 長いものは10cm程度に切る
- 風通しの良い場所で、1週間ほど日陰干しし、完全に乾燥させる
一般的なお茶と同じように、急須にお湯を注いでしばらく蒸らしたのち、飲用します。
のどが渇いた時の水分補給に飲むほか、老廃物の排出を助けるため、寝る2~3時間前に飲むのがベスト。
ヨモギ

基本情報
ヨモギは「和製ハーブの女王」と言われています。
子どものころ、葉っぱを絞って出てきた汁を擦り傷や切り傷につけていた記憶があります。
| 採集時期 | 3~7月 |
| お茶に使う部位 | 葉 |
| 主な成分 | 葉緑素、食物繊維、ビタミンA・B1・B2・B6・C・E・K、βカロテン、 シネオール、タンニン、ツヨン、鉄分、リン |
| 期待できる健康効果 | 喘息・貧血・生活習慣病・骨粗鬆症予防、便秘解消、コレステロールの低下、 保温効果、抗酸化作用、デトックス効果、鎮痛・抗菌効果、美肌効果、止血、 婦人科系疾患の改善、健胃効果、リラックス効果 |
| お茶以外の利用法 | 草餅、天ぷら、おひたし、あえ物 お灸、染料、入浴剤、虫よけ、殺菌、よもぎ蒸し |
ヨモギ茶の作り方
- 茶色く乾燥した部分や汚れを取り除き、水洗いする
- 5cm程度の長さに切って蒸す
- 3~4日天日干しする
- フライパンで乾煎りする
急須にお湯を注いでしばらく蒸らしてから飲むもよし、煮だして飲むもよしです。
*蒸すのは省略しても構いませんが、蒸したほうが味わい深いお茶になります。
期待する効果によって、飲むタイミングを変えると効果的だが、基本的にはいつ飲んでも大丈夫。
- 貧血や冷え性、血流の改善、美容効果:食前
- リラックス効果:寝る1時間前
タンポポ

基本情報
日本の在来種であるタンポポも外来種の西洋タンポポもどちらもお茶作りに使えますが、西洋タンポポのほうが苦みが強いです。
見分けるには花のつけ根にある総苞片(そうほうへん)を見て、下に反り返っていれば西洋タンポポ、上向きなら日本タンポポです。
| 採集時期 | 3~5月 |
| お茶に使う部位 | 根、花・葉 |
| 主な成分 | イヌリン、ビタミンA(βカロテン)・B・C・D・E、リボフラビン、 カルシウム、鉄、マグネシウム、カリウム、リン、亜鉛 |
| 期待できる健康効果 | 消化を助ける効果、利尿効果・デトックス効果、抗酸化作用、リラックス効果、 血液サラサラ効果、腸内環境の改善、骨密度の改善 |
| お茶以外の利用法 | 根:きんぴら 葉・花:炒め物、天ぷら |
タンポポ茶の作り方
タンポポコーヒー
- 掘り出した根をブラシ等を使ってしっかりと洗浄する
- 適当な長さに切り、さらに数ミリ程度にスライスする
- 日当たりのいい室内で時間をかけて乾燥させる
- フライパン(中弱火)で香ばしい匂いがするまでじっくり20~30分ほど乾煎りする
乾燥させた根を10分から15分程度とろ火で煮だして飲むと、深い味わいが楽しめます。
花・葉のお茶
- 花や葉を洗って汚れを落とす
- 沸かした湯に入れて10分ほど蒸らす
いつ飲んでもよいが、脂っこい食事のときには食事と一緒に、飲みすぎや食べ過ぎのときには食後に飲むのがおすすめ。
スギナ

基本情報
生命力が旺盛で、畑の厄介者のスギナは、おひたしなどで食べられるツクシと同じ根から育ちます。
| 採集時期 | 4~7月 |
| お茶に使う部位 | 葉 |
| 主な成分 | カルシウム、マグネシウム、リン、カリウム、ビタミンA・C・E、鉄分、 シリカ、ケルセチン、ケイ素、チアミナーゼ |
| 期待できる健康効果 | 利尿作用、むくみの改善、抗酸化作用、美髪効果、アンチエイジング効果、 血糖値の上昇抑制、疲労回復、免疫力の向上、貧血・骨粗しょう症の予防 |
| お茶以外の利用法 | 入浴剤、ふりかけ |
スギナ茶の作り方
- 根元から切り取ったをよく洗い、汚れを取り除く
- 適当な長さに切る
- 重ならないように新聞紙などの上に広げ、風通しの良い場所で1週間ほどしっかりと乾燥させる
飲む際には、水と乾燥した葉っぱを鍋に入れ、火にかけて沸騰させたあと、弱火で1~2分ほど煮だします。急須に熱湯を注いで、3~4分蒸らして飲むことも可能です。
いつ飲んでもOKだが、朝の一杯や仕事の合間に飲むのが特におすすめ。
クローバー

基本情報
クローバーは、海外では古くからハーブ療法や民間医療で利用されてきました。
| 採集時期 | 5~10月 |
| お茶に使う部位 | 花・葉 |
| 主な成分 | アカツメクサ:イソフラボン、シリカ、コリン、カルシウム、レシチン、タンニン、 フラボノイド、クマリン、フェノール配糖体、フラボン類、サリチル酸塩、 シアン配糖体、クマリン、精油 シロツメクサ: |
| 期待できる健康効果 | アカツメクサ:更年期障害の改善、肌トラブルの改善、精神安定、血液の浄化作用、 抗カタル・抗炎症作用、リンパ系の浄化、 シロツメクサ:消化不良・不眠症の改善、不安の軽減、咳止め、利尿作用、 |
| お茶以外の利用法 | おひたし 目の洗浄 |
クローバー茶の作り方
花茶
- 朝摘み取った花を水の中でゆすり洗いし、汚れや虫、茶色く乾燥した部分などを取り除く
- 水気を切り、日陰干しでパリパリになるまで乾燥させる
- 香りが弱いようなら、フライパンで乾煎りする
急須に乾燥した花を入れ、熱湯を注いで、数分蒸らした後、いただきます。蜜が入っているので、ほんのりとした甘さが感じられるかもしれません。
葉のお茶(シロツメクサ)
- 葉っぱをきれいに洗い、水気をふき取る
- 日陰干しでパリパリになるまで乾燥させる
乾燥した葉を熱湯に入れ、とろ火で水の量が半分になるくらいまで煎じて飲みます。
いつ飲んでもOKだが、女性ホルモンのバランスを整えたい場合は、アカツメクサの花茶を就寝前か食後が効果的。
オオバコ

基本情報
子どもの頃、2本の茎を交差させて、草相撲を楽しんだことはありませんか。
在来種と外来種がありますが、どちらも同様の効果が期待できます。
| 採集時期 | 全草:7~8月 種:9~10月 |
| お茶に使う部位 | 葉・茎・種 |
| 主な成分 | サイリウム、プランタギニン、フラボノイド、タンニン、ポリフェノール、 アウクビン、ビタミンA |
| 期待できる健康効果 | 葉:健胃・整腸作用、利尿作用、コレステロール・血糖値の上昇抑制、咳止め、 保温効果、抗炎症作用、粘膜の修復作用 種:葉の効果+視力回復効果 |
| お茶以外の利用法 | ふりかけ・かき揚げ |
オオバコ茶の作り方
- 摘み取った葉・茎・種をよく洗って、水気を切る
- 風通しの良い場所で、パリパリになるまで1週間程度乾燥させる
- 葉を細かく砕く
鍋に水と乾燥させた葉・茎・種を適量入れ、弱火で約5〜10分煮出し、茶葉を濾せばオオバコ茶の出来上がりです。
食前に飲めば、消化を助け、便秘の予防や改善に役立ち、むくみの解消には、朝に飲むのがおすすめ。
スイバ

基本情報
似たような雑草のギシギシ(こちらも食用可)とは、花穂や葉の色(赤みを帯びている)、葉の形(矢じりのように下がとがっている)、葉柄(長い)で見分けがつきます。
| 採集時期 | 3~4月 |
| お茶に使う部位 | 葉・茎・根・花 |
| 主な成分 | ルチン、ビテキシン、ヒペリン、クエルセチン、ケンフェロール、ミリセチン、 シュウ酸、シュウ酸カリウム、シュウ酸カルシウム、アントラキノン誘導体、 タンニン |
| 期待できる健康効果 | 緩下作用、利尿作用、収斂作用、健胃・解熱効果、抗がん作用、むくみ予防 |
| お茶以外の利用法 | 葉:おひたし、あえ物 根:殺菌(湿布) |
スイバ茶の作り方
根のお茶
- 掘り出した根を丁寧に水洗いする
- 水気を採り、天日干しでしっかりと乾燥させる
1日量10グラム程度を500㏄ほどの水に入れ、半量になるまで弱火で煎じたものを、1日3回に分けて飲みます。
全草のお茶
- 切り取った葉・茎・花などを丁寧に水洗いする
- 水気を採り、天日干しでしっかりと乾燥させる
- 乾燥した茶葉を細かく刻む
ハーブティーのように、急須に乾燥した茶葉を入れ、熱湯を注ぎ、数分蒸らしていただきます。
いつでもOK。
ハコベ

基本情報
春の七草(ハコベラ)として有名です。
| 採集時期 | 3~6月 |
| お茶に使う部位 | 葉・茎 |
| 主な成分 | ビタミンA・B・C、フラボノイド、サポニン、クマリン、カルシウム、鉄分、 葉緑素、亜鉛、 |
| 期待できる健康効果 | 健胃・整腸作用、利尿作用、消炎作用、皮膚炎の改善、解毒・止血作用、 歯槽膿漏の改善、便秘解消、免疫力向上、母乳の分泌促進、抗酸化作用 |
| お茶以外の利用法 | サラダ、おひたし、天ぷら ハコベ塩、歯磨き |
ハコベ茶の作り方
- 切り取った葉・茎(花が付いていてもOK)を丁寧に水洗いする
- 天日干しでしっかりと乾燥させたのち、細かく刻む
急須に茶葉を入れて熱湯を注ぎ、5分ほど蒸らせば出来上がり。
食事の際に一緒に飲むのがいち推し。
カラスノエンドウ

基本情報
「ピーピーマメ」といったほうがわかりやすいかもしれません。
| 採集時期 | 3~6月 |
| お茶に使う部位 | 花・葉・茎・実 |
| 主な成分 | ビタミンB1、ポリフェノール、アイピン、クエルシトリン |
| 期待できる健康効果 | 血行促進、咳止め、むくみ・便秘の解消、貧血・冷え性・高血圧・動脈硬化予防、 胃もたれの緩和、新陳代謝の向上、発毛・育毛促進 |
| お茶以外の利用法 | おひたし、天ぷら |
カラスノエンドウ茶の作り方
- 採集した葉・茎・花をきれいに水洗いする(アブラムシが付いていることが多いので要注意!)
- ざる等に広げ、1週間くらい天日干しにする
- 適度な大きさにカットしたのち、フライパンで乾煎りする
鍋に水と乾燥した茶葉を入れ、弱火にかけて好みの濃さまで煮だして飲んでも、急須に熱湯を注ぎ、蒸らして飲んでもOK。
いつ飲んでもOK。
ナズナ

基本情報
春の七草の1つで、「ぺんぺん草」とも呼ばれています。
| 採集時期 | 10~5月(秋がベスト) |
| お茶に使う部位 | 葉・茎・花・種(土より上に出てる部分) |
| 主な成分 | サポニン、カリウム、コリン、フマル酸、ジオスミン、ビタミンA・C・E・K、 カルシウム、鉄分、アミノ酸、フラボノイド、ルチン、スルフォラファン、 シトステロール、クロロゲン酸、アセチルコリン |
| 期待できる健康効果 | 利尿・解熱・止血・血圧降下作用、殺菌作用、生理不順の改善、生活習慣病の改善、 ガン・皮膚病・骨粗鬆症などの予防効果 |
| お茶以外の利用法 | 七草がゆ、サラダ、あえ物 洗眼 |
ナズナ茶の作り方
- 刈り取った葉・茎・花を水洗いする
- パリパリになるまで陰干しする
普通のお茶のように飲むことも、鍋に水と乾燥した茶葉を入れ、煮だして飲むこともできます。
いつ飲んでもOK。
山野草のブレンドティー

山野草は、1種類だけを使ってお茶にすることもできますが、複数を混ぜてブレンドティーにすることも可能です。
日頃畑や庭の雑草に悩まされている人は、引っこ抜いた草の中からお茶にできるものを選び、まとめて水洗い、乾燥させておくと、1週間後くらいには疲れをいやす飲み物が手に入りますよ。

まとめ
今回は、16種類の山野草を使ったお茶について紹介しました。
- ツバキ
- アカマツ
- スギ・ヒノキ
- クマザサ
- 淡竹
- サルトリイバラ
- スミレ
- ドクダミ
- ヨモギ
- タンポポ
- スギナ
- クローバー
- オオバコ
- スイバ
- ハコベ(ハコベラ)
- カラスノエンドウ(ピーピーマメ)
- ナズナ(ぺんぺん草)
普段何気なく眺めている樹木や、厄介者扱いされている雑草の中には、食用に栽培されている野菜などより栄養価が高く、健康効果が期待できるものがたくさん存在します。(ほかにも、しそ科のホトケノザ、ヒメオドリコソウ、ノアザミ、ヒバ、イチョウ、ゲンノショウコ、タラなど、数え切れません。)
なお、それぞれに多少異なるお茶の作り方を紹介しましたが、栄養分や健康成分を効果的に摂るには、どの山野草も蒸し、揉み、乾燥、焙煎、煮出して飲むのがいちばんです。
ただ、そこまでするのは手間がかかりますし、生の山野草を切って、熱湯を注いで作るお茶にも効果がないわけではありません。(サヴァイヴァル番組では生を鍋に入れて煮出していました。)
SDGsにもなりますし、山野草によるお茶を試してみませんか。ただし、採るのも飲むのも自己責任でお願いします。