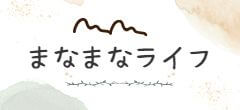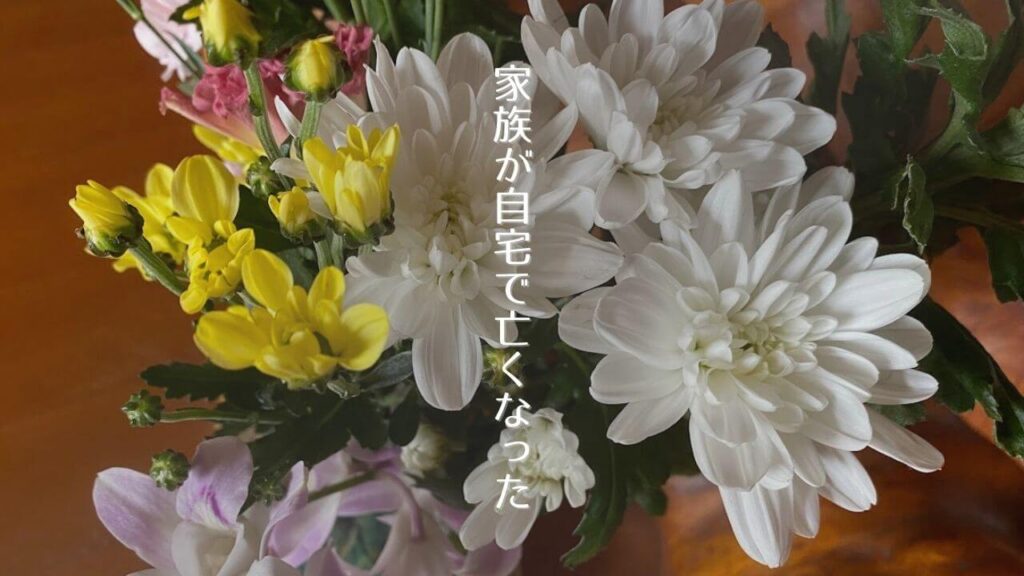ある日突然、自宅で愛する家族の一員が亡くなっているのを発見したら、あなたはどうしますか。
最初の対応を間違うと、葬送までのプロセスに時間がかかるだけでなく、あらぬ疑いをかけられたり、周囲に迷惑をかけてしまう可能性も出てきます。
今回は、在宅死が増加傾向にある現在、自宅で家族が亡くなっているの発見した際、遺族がどう対応すべきか、実例付きで紹介します。
在宅死を発見した際の正しい対応

自宅で家族が亡くなっているのを発見した際、どこに連絡するかは
- 生死が不明
- 亡くなっていることが確実な場合
- かかりつけ医有り
- かかりつけ医無し
によって変わります。
生死の判断ができない場合
例えば、なかなかお風呂から出てこないので見に行ったら、湯船に浸かったまま動かなくなっていたなど、生死の判断が付かないときは、即座に救急車を呼んでください。
亡くなっていることが明らかな場合
身体が冷たい、死斑が出ているなど、発見した時点で既に亡くなってから一定の時間がたっている場合、かかりつけ医がいるのといないのではファーストコンタクトが異なります。
かかりつけ医がいる場合
亡くなった人の健康状態や病状をよく知るかかりつけ医がいる場合は、まずそのかかりつけ医に連絡を取ると、次にすべきことを指示してもらえます。
在宅で終末期の緩和ケアを受けていたり(看取り)、高齢だったりと、亡くなられることがある程度予測できていた場合、たいていは医師がすぐに駆け付け、死後診察の後、死亡診断書を書いてくれます。
一方、かかりつけ医がいても、最後の診察からかなり時間がたっているようなら、警察に連絡するように提言される可能性が高いです。
また、たとえ最初に連絡した時点で警察に連絡するように言われなかったとしても、かかりつけ医による死後診察の結果、生前の健康状態(または病状)と死因の因果関係がはっきりしない場合は、医師のほうから警察に届出をすることになります。
これは「死因が断定できない死=不審死」と見なされるためです。
*死後診察で、死因が生前の傷病に関連していることが判明した場合、警察は呼ばれず、かかりつけ医により死亡診断書が交付されます。
警察が到着した後の流れ
警察が到着した後は、事件性の有無を確認するために、
①第一発見者を始めとする家族への事情聴取
②現場検証
③検視(犯罪性の有無を判断するために警察官が行う遺体や現場の調査)
と続き、事件性がないと判断されれば、さらに
④検案(外見から死因や死亡推定時刻等を判断するために監察医や医師が行う医学的判断)
が行われ、最終的に死亡診断書と同等の死体検案書が発行されます。
なお、検案については、その場に医師がいない限り、自宅から場所を変えて行われるのが普通です。
かかりつけ医がいない場合
かかりつけ医がいない場合は、警察に連絡します。
警察が到着した後の流れは、上述の通りです。
NG対応
明らかに亡くなっている家族を発見した際、やってはいけないことが2つあります。
1つ目は救急車を呼ぶことです。
救急車は、命を救うために使われるべきものであり、ご遺体を搬送するものではありません。
家族が亡くなったという事実を受け入れられず、どうにかしてほしいという思いから救急車を呼びたくなる気持ちはわかります。けれど、そのせいで本当に必要としている誰かのもとに救急車が届かず、その人を救えなくなる可能性があるとしたらどうでしょう。
亡くなってしまった家族のために、救急車を手配すべきでないことは自明の理です。
2つ目のNG対応は、ご遺体や現場に手を加えることです。
遺体も亡くなられた現場も、発見時のままにしておかないと、警察や医師が正しい判断をする妨げになり、調査に時間もかかります。
それだけでなく、事件性を疑われて無い腹を探られることになるため、自業自得とはいえ、遺族は不快な思いをすることになるでしょう。
実例1(OK対応):91歳女性の在宅死
こちらはつい最近、遠い親戚の身に起こったことです。
同居家族:なし。月に1度、県外に住む息子(59歳)が様子見や買い物のために2~3日帰省。週に2回、訪問介護サービスあり。老人ホームや介護施設への入居は本人が拒否。
亡くなるまでの健康状態:人工肛門を装着。心肥大あり。疲れやすくなってきたものの、基本的な生活はほぼ一人でできる。
亡くなる2日前、帰省中だった息子と普通に食事をとる。同日の夕方、「おなかが痛い」と電話連絡あり。息子が「救急車を呼んで病院に行くように」勧めるも、本人が拒否。介護サービスの人にも連絡して話をしてもらうが、やはり「病院には行かない」の一点張り。
発見時の状況:翌日、電話をしても一向につながらないため、息子が介護サービスの方に母親宅を訪問してくれるよう依頼。介護サービスの方が冷たくなった遺体を発見し、息子と警察に連絡する。
その後の展開:警察が到着し、事情聴取と現場検証を終えたのち、遺体を警察の遺体安置所に搬送する。検視が行われ、死体検案書が発行される。
残念ながら、独居老人が増えるにつれ、こういった孤独死も増加傾向にあるようです。
参考資料:「平成22年度版高齢社会白書(全体版)第1章 第3節 3(2)孤立死の増加」
実例2(NG対応):89歳男性の在宅死

これは今から20年以上前に、うちの家族に起こったことです。
同居家族:妻(87歳)・息子(63歳)・息子嫁(59歳)
亡くなるまでの健康状態:命の危険に関わるような持病なし。老化により足元がおぼつかず、亡くなる2日前にも転んで全身に打ち身や擦過傷を負い、かかりつけ医の診察を受けていた。
発見時の状況:朝食の時間になっても起きてこないため、夫婦の寝室(6畳和室)に妻が様子を見に行ったところ、反応がなく、部屋に汚物の臭いもしていたため、他の家族を呼ぶ。
発見後の対応:119番に通報して救急車を要請する。救急車の到着前に、遺体の下着を新しいものに替え、汚れたほうはビニール袋に入れて裏山に遺棄する。
その後の展開:救急車が到着したものの、すぐに撤退。救急隊員からの連絡を受けて、別の種類の救急車と警察車両が到着。警察だけが残り、事情聴取と現場検証が始まる。
遺族は、発見時に着用していた下着を処分したこと、遺体の体表に複数のあざや傷があることに関して厳しく問いただされるも、かかりつけ医による死後診察の結果と、別々に聴取した3人の証言が完全に一致していたこともあり、最後はお叱りの言葉とともに警察も退去。
後日、医師から書類(死亡診断書か死体検案書かは不明)を受け取る。

汚れた下着のままひと目にさらされるのはイヤだろう思って着替えさせただけなのに、あんなに絞られるとはねぇ。

…。
身内の恥をさらしてこの話を終えるのは、なんとも忍びないので、祖父の死にまつわるほっこりエピソードも1つ。
実は、祖父は亡くなった日の朝5時過ぎに1度寝床から起き上がり、隣に寝ていた祖母のもとに行き、黙って手を握ったそうです。
気づいた祖母が「トイレ?」(前立腺肥大で尿が出なくなったことが過去に2度あったため)と声をかけたものの、何も言わずにまた布団に戻ったとか。
本当のところはわかりませんが、家族の間では最後に祖母にありがとうの気持ちを伝えたかったんだろうということになっています。
他の遺族にはお別れを言う間もありませんでしたが、もしかすると祖父のように、人生の晩年を大きな苦痛に煩わされることなく過ごし、眠っている間に静かに息を引き取るというのが、最高の人生の幕引きなのかもしれません。
余談になりますが、祖母は祖父が亡くなった2か月ほど後、入浴中に突然脳卒中を発症し、その2日後に病院で永遠の眠りにつきました。
いつもトロトロと歩いていた祖父と違い、サッサ、サッサと歩いていた祖母。きっと三途の川の手前あたりで祖父に追い付き、「さっさと行くよ」なんて言いながら、一緒に彼岸へと渡ったのではないでしょうか。
在宅死の今後
厚生労働省の「【テーマ6】人生の最終段階における医療・介護」によると、2021年の死亡場所は
| 医療機関 | 67% |
| 自宅 | 17% |
| 介護施設・老人ホーム | 14% |
となっています。
つまり、2021年の時点では10人に1~2人が自宅で亡くなっているということになります。
一方、意識調査における「最期を迎えたい場所」に関しては、
| 医療機関 | 41.6% |
| 自宅 | 43.8% |
と、より多くの人が医療機関よりも自宅を希望していることがわかります。
そして国は、そういった国民の希望に添えるように、在宅での医療(訪問医療)や介護に関する支援や体制を拡充する方向で動いています。
そういった事実を鑑みる限り、今後はますます在宅死が増加するのではないでしょうか。
まとめ
今回は、自宅で亡くなっている家族(在宅死)を発見した際の正しい対応とNG対応について、実例付きで紹介しました。
覚えておきたい!自宅で家族が亡くなっているのを見つけた時のファーストコンタクト
- 生死の判断ができない:救急車(119)
- かかりつけ医がいる:かかりつけ医
- かかりつけ医がいない:警察(110)